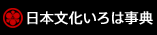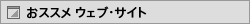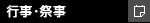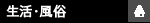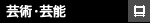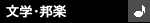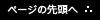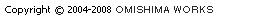3月3日は、ひな祭り。雛人形を飾る風習は、災厄を人形(ひとがた)にのせて川に流した「流し雛」が始まりとか。
(今も全国各地で行われてますね)
特集第1回目は、雛祭りに関するマメ知識を紹介します。
≫ ひな祭りの基本情報はひな祭りのページをご覧ください。

赤ちゃんが生まれて初めて迎える3月3日を初節句と言い、初節句の1ヶ月程前までに母方の両親が贈るのが一般的なようです。しかし、母方父方両方の両親がお金を出し合ったりするケースも珍しくありません。最近は若夫婦と子どもだけの家族も増え、どちらの両親も孫が遠く離れていて心配だからでしょうか。どちらにしろ、孫を想う両親の気持ちが雛人形に託されるのですね。
また、雛人形は一人一体なので、親戚や友人が女児の健やかな成長を願って贈り物をする場合は、雛人形ではなく、市松人形などのケースに入った人形を贈るようです。

二十四節気の1つ、雨水(2005年は2月18日)に雛人形を飾ると良縁に恵まれるとされていますが、立春(3月4日)から2月中旬に飾られることも多いようです。また、片付けは早ければ早いほど良いとよく耳にしますが、正式には啓蟄(2005年は3月5日)に片付けるようです。
※この日に片付けるのが難しい場合は、人形を後ろ向きにすると、「眠られた」「帰った」という意味を持ち、片付けたことと同様になるそうです。
各地各様で違いがあるようですので、この機会に是非郷土やご近所の風習を調べてみては!?
菱餅は、もともとお正月の鏡餅だったようです。昔は春分から1ヶ月間がお正月として祝われていたので、ひな祭りの時期は、今で言う鏡開きの時期だったのかもしれませんね。詳しい由来は定かではないですが、何時しか菱餅はひな祭りの縁起物として飾られるようになったようです。また、白・青・桃の3色はそれぞれ、雪の大地(白)・木々の芽吹き(青)・生命(桃)を表しており、自然のエネルギーを授かる意味が込められています。
あられは、乾燥した餅を小さく分けて焼いたものです。ひな祭りの行事の最後に菱餅をあられにして食したのが始まりではないかと言われています。
蛤の2枚殻を離すと他の貝殻と絶対合わないことから「良縁に恵まれる」、また殻が固く閉じている様から「貞操を守る」といった意味を持ちます。
白酒は「桃花酒」とも言われ、ひな祭りがまだ盛んでない頃から桃の節句に飲まれていました。自然の力を体内に入れることで、厄払いをする意味があります。
| 雛のつるし飾りまつり | 静岡県東伊豆町稲取温泉 | 1月20日〜3月31日 | ひな壇の両脇につるし飾りを赤い糸で結びつけて飾る、江戸時代より続く全国でも珍しい風習です。 |
| 柳川雛祭り・さげもんめぐり | 福岡県柳川市 |
2月11日 〜4月3日 |
色とりどりの布で創られた鞠のような「さげもん」が主役の祭り。展示会やパレードがあります。 |
| 京のひな流し | 京都府京都市 | 3月3日 | 編んだわらに乗せたひな人形をみたらし川に流し、子供たちの無病息災を祈る神事。 |
| 雛の里・八女ぼんぼりまつり | 福岡県八女市 |
3月1〜31日 | 町家や商店100カ所以上で、雛人形や関連道具を展示。パレードなども開催。 |
| 雛祭(雛流し) | 和歌山市加太 | 3月3日 | 務めの終わったお雛様を海に流し供養する神事。各地で流される流し雛はここが終着点となる。 |
| もちがせ流しびな | 鳥取県八頭郡 | 4月11日 | 菱餅や桃の小枝を添えて災厄を託して千代川に流します。昭和60年に県無形民俗文化財に指定。 |
| 吉野川流し雛 | 奈良県五條市 | 4月3日 | 竹の皮で作った船に千代紙などで作られたお雛様を乗せて吉野川に流します。吉野川に流したお雛様は、紀ノ川を下り、女性の病封じ・安産・子宝の神様である紀州淡島神社へと旅します。 |
≫ 雛祭り
≫ 上巳の節句
≫ 端午の節句
≫ 五節句
≫ 振袖
≫ 餅
≫ 寿司